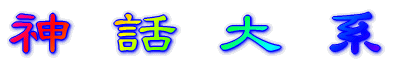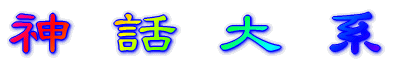|
ルテラに住まう各種族には、それぞれに伝わる独特の神話があります。
それらは互いに影響し合ったり、あるいは対立しつつ、大きな流れを形成しています。
ここでは、その成立の古いものから順に、紹介していくことといたしましょう。 |
|
| ドリダリア神話 |
「古代種族」であるドリダリア族。
その神話は、この世界に伝わる最も古い神話体系のひとつですが、他の種族の神話に比べ、際だった特徴がある。
それは、「自分たちの祖先がこの世界の創世を手伝った」という設定になっているということだ。
他の種族の神話では、世界を創世したのは(それぞれに異なる名前のものではあれ)あくまでも「神」または「神々」であるのだが、ドリダリア族は「自分たちも創造の手伝いくらいはした」と主張しているのである。
これは、このルテラ世界の「創造神」というのが、(一部種族の伝承を除き)基本的に「竜」であるということの影響が強いかも知れない。外見がもっとも良く「竜」に似ている彼らとしては、「馬」だの「鬼」だの「猿」だのに似た他種族に比べ、自分たちの方がはるかに優秀で正当な「人間」なのだ、という自負があるようである。
神はこの世界の骨を造られ、その骨より我らを造られた。
そして、我らは神と共に、この世界の血と肉とを造った。
この世界ができあがったとき、そこは平和ではあったが、退屈そのものであった。
我らは神に願い、敵を造っていただくことにした。
神は我らの願いを聞き届けられ、ヴァルヒャリアの魔族らをお造りになった。
と、ヴァルヒャリア族との関わりをそのような形で説明している。
ここで、自分たちが造ったのではなく、「神に頼んで造ってもらった」となっているのは、その後の大戦争の結果、ついにヴァルヒャリア族を滅ぼすことができず、自分たちも大打撃を受けてしまったという事実に対する伏線なのであろう。(初期の伝承では、「我らが造った」ということになっていたらしい)
我らは神に願った。
もう十分です。我らが間違っていたようです。
確かに我らは、敵を求めましたが……
あれほどの化けものどもまで求めたつもりはありませんでした。
どうかあの連中を消してしまってください。
すると、神はお怒りになった。
身勝手な愚か者どもめ!
そもそも、この大戦乱はお前たち自身が望んだことではないか!
わたしはお前たちに、平和な良き世界を用意してやったものを……
思い知るがよい! おのれ自身の愚かしさを!
そして、我が怒りの大きさを!
かくて、大いなる災いの日は来た。
自信過剰で傲慢な彼らではあったが、自己批判や懺悔の類と無縁であったわけでもなく、自分たちの愚かしさが「神の怒り」をまねき、その結果として「魔族ら」もろとも「種族半殺し」の憂き目に遭ってしまった……ということになっている。
神は我らの数を減らし、また彼らの数をも減らした。
そして、この大地の支配者としての地位を、お取り上げになった。
神は新たに「角ある者たち」と「角なき者たち」とをお造りになった。
そして言われた。
○○○○……。
この神の台詞以降の部分は、現存するどの資料からも欠落している。
おそらく、新たに造られた二つの種族のうちどちらかに、地上の支配権を与えた……というような意味のことだったのではないかとも言われているが、定かではない。
その内容を嫌った後世の者たちが消してしまったのだとも、また、神の慈悲により、その部分は後で取り消され、今に至るまで新たな決定がなされていないのだとも言われている。
いずれにせよ、彼らは未だに、このような誇りを持っている。
我らはこの世界の骨から造られた。
他の連中は、この世界の血肉から造られた。
そして、その血肉を造ったのは、我らの祖先たちである。
……と。
|
|
| ヴァルヒャリア神話 |
もう一つの「古代種族」たるヴァルヒャリア族。
彼ら(今では彼女らというべきだろうが)の神話体系も、かなりユニークなものである。
彼らは、他の種族とは異なり、「竜」を「神」であると認めていない。
いえ、そもそも彼らは、この世界の創造神の存在そのものを認めていないのである。
ルテラはここにあった
誰も生まれることもなく
それ自身の他には何もない
そのころから
ルテラはここにあった
そして、大いなる時が流れ
いつしか我らは、ここにいた
そして今も、ここにこうしている
人が、物心ついてからの記憶しか留めていないのと同じく、種族もまた「いつのまにかここにいる」のだ……とする考え方は、いささか拍子抜けするほどに慎ましいものである。彼らはそこに、何ら哲学的な意味合いや必然性を求めようとはしていない。
あいつらは、何も考えず、ただただ走ってばかりいる、本当の意味での「馬鹿」どもだ。
などとドリダリア族から批判されることの一因ともなる、この控えめな自己主張こそが、まさにヴァルヒャリア族の神話の特徴と言えるだろう。
ただし、その控えめな初期の態度とは裏腹に、彼らは一時期、極めつけに傲慢となり、凶猛にもなった。
我らの翼は全天を覆いつくし
我らの蹄は全地を踏みかためた
天の果て、地の端にいたるまで
我らの知らぬところ、ひとつとてなく
生きとし生けるものは
その血の一滴に至るまで我らのものとなった
もはや我らの意思によらずしては
木の葉が風にそよぐこともなく
野の草が花を咲かすこともない
天は我らが翼のためにあり
地は我らが蹄のためにある
もはや我らの望まぬ限り
陽が地の表を照らすこともなく
川が海に向けて流れ下ることもない
事実上、一時期のルテラは彼らの完全支配下に置かれていたのだというこの行(くだり)は、明らかにドリダリアの神話と矛盾・対立している。彼らによれば、このルテラに最初に登場した高等生物は、彼らヴァルヒャリア族のみだというのである。
そして、ドリダリア族については、このように語られる。
彼らは、いつの間にかそこに現れた
そして、いつの間にかそこで増えていた
おお、おぞましき者ども!
地を這う者どもよ!
彼らの吐息により天は汚され
彼らの汚物により地は辱められた
なんともひどい言い方であるが、彼らがドリダリア族に感じていた嫌悪感と偏見とを、これほど如実に証明する言葉はない。
どちらが先にいて、どちらが後から来たのか……
そして、どちらが先にしかけたのか……
いずれにせよ、ヴァルヒャリア族とドリダリア族との間に、凄まじいまでの大戦争が繰り広げられたことは確かである。
我らは彼らを追い落とし
この地の表よりぬぐい去る
戦士(レムルハ)たちよ
無慈悲なるを以て良しとせよ
大いなるアグネアの光もて
汚れた者どもを焼きつくせ
清めよ! 清めよ!
我らが大地を清めつくせ!
ヴァルヒャリア族の戦士たちは、この言のごとくにまったく無慈悲そのものであり、彼らが通り過ぎた後には、草木の一つも生えぬほどであったという。
アグネアと呼ばれた兵器がどのようなものであったのか、その正確な資料は現存しない。ただ、一瞬にして街を一つ跡形もなく消し去ってしまうほどの、強烈な大量殺戮兵器であったことは確かなようである。
ドリダリア族も負けてはいなかった。
ヴァルヒャリアのアグネアに対抗するかのように、ヴリトラと呼ばれる超兵器を開発し、報復したのである。
ああ、どこもかしこも真っ黒こげ
いったいどこに行ったの?
あんなに咲き乱れていた花たちは
わたしたちは、もう走れない
どんなに走っていったとしても
目にするものは、ただ焼け焦げた大地だけ
おお、あの恐ろしく逆巻く黒雲
いったいどこに行ったの?
あれだけあちこちでさえずっていた鳥たちは
わたしたちは、もうとても飛べない
どこまで飛んでいったとしても
聞こえてくるのは、痛ましい呪詛の声ばかり
突如、それまでの男々しい文体から一変し、女言葉ばかりが続くようになる。
ヴァルヒャリアの男(レムルハ)たちが全滅し、女(ドリュテス)たちしかいなくなってしまったためだという。完全体とも呼ばれた女王(ゲリュペス)たちですら、そのほとんどがヴリトラの灼熱の劫火の前に為す術もなく焼き滅ぼされてしまっていた。
ああ、わたしたちは
死の使いと成り果て
世界の破壊者となってしまった
剣は剣となり
炎は炎となって
われとわが身にふりかかり
すべてを打ち砕き
何もかも焼きつくしてしまった
この大戦のもたらした惨禍は凄まじいものだった。
ヴァルヒャリアもドリダリアも、それぞれの人口の実に99%以上を死滅させてしまうという、まこと驚愕すべき結末を迎えたのである。
さすがに自らの所行を恥じた彼らは、以後はそれぞれの本拠地に戻り、ひっそりと隠れるようにして、細々とその命脈を保つこととなる。
そして、もっとも激しい戦場となった大地は、いつしかカルナ・ルヴァ(宿業の土地)と呼ばれるようになったという。 |
|
 |
|
★当サイトに掲載されている小説、詩、その他の作品の著作権は三角隼人に帰属します。無断での引用、転載等はご遠慮下さい。★
|